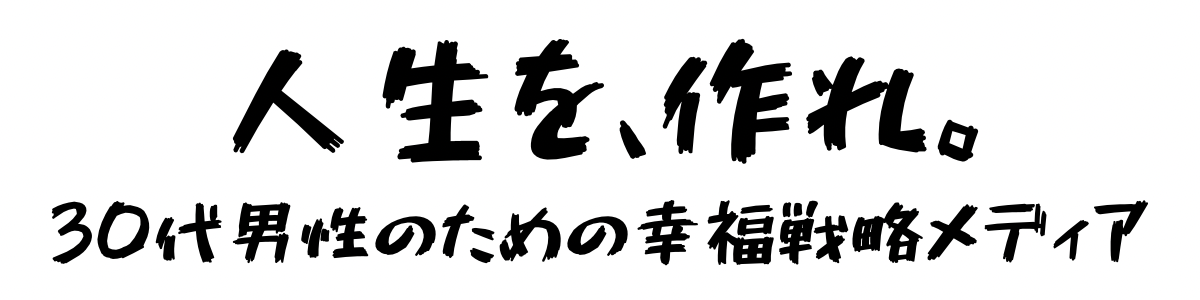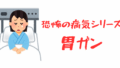肝臓がんは、その名の通り肝臓にできる悪性腫瘍です。
日本では、がんによる死亡原因の上位に位置する疾患のひとつであり、特に40代以降の男性に多く見られます。
恐ろしいのはその“静かさ”です。
肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれるほど、ダメージを受けても症状が出にくいため、発見が遅れることが多いのです。
なぜ肝臓がんは怖いのか?
① 自覚症状が出にくいまま進行
肝臓は、多少の障害を受けても沈黙を保ちます。
そのため、がんがかなり進行してからようやく症状が現れるケースが多いです。
代表的な症状は次の通りです:
- 倦怠感(疲れやすさ)
- 食欲不振
- 体重減少
- 黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)
しかし、これらはいずれも「忙しいだけ」「年齢のせいかも」と見過ごされがちな症状です。
② 背後にある慢性肝炎や肝硬変
肝臓がんの多くは、慢性肝炎や肝硬変から発生します。
特に、C型肝炎ウイルス(HCV)やB型肝炎ウイルス(HBV)による感染歴がある方は、知らないうちにリスクが高まっている可能性があります。
肝炎ウイルスの感染は、輸血・性行為・母子感染などでも起こり得ます。
自覚がなくても、過去のリスク行動があれば検査を受けるべきです。
③ 発見が遅れると治療の選択肢が狭まる
肝臓がんの治療には、以下の方法があります:
- 外科手術による腫瘍の切除
- 肝臓移植(条件を満たす必要あり)
- 抗がん剤・放射線治療
- カテーテルによる塞栓術(TACE)
しかし、がんが進行しすぎると手術や移植の対象外となることが多く、根治は難しくなります。
「働き盛りの男性」に多い理由
肝臓がんは、40代・50代の男性に多いがんとしても知られています。
その背景には以下のような要素があります:
- 長年の飲酒習慣(アルコール性肝炎→肝硬変)
- 肝炎ウイルスの放置
- 不規則な生活・過労による免疫低下
- 健診を受けない(時間がない、健康だと思っている)
つまり、「健康には自信がある」と思っている人ほど危険なのです。
肝臓がんを予防するには?
肝炎ウイルスの検査を受ける
まず最初にやるべきことは、B型・C型肝炎ウイルスの感染有無の検査です。
日本では40歳以上であれば無料で受けられる自治体もあります。
感染していた場合は、適切な治療によって発症リスクを抑えることが可能です。
特にC型肝炎は、現在ではほぼ完治可能な時代になっています。
アルコールは「適量」を超えない
大量飲酒は、脂肪肝→アルコール性肝炎→肝硬変→肝がんという流れをたどることがあります。
適量とは、1日あたり純アルコールで約20g(ビール500ml程度)までとされています。
毎晩の飲酒が習慣化している方は、「休肝日」をつくることが重要です。
定期的な肝臓の超音波検査・血液検査
肝機能を確認する血液検査(AST, ALT, γ-GTPなど)や、肝臓の画像検査(エコー・CT)は、早期発見に有効です。
特に以下に当てはまる方は、年1回以上の検査を推奨します:
- 飲酒習慣がある
- ウイルス性肝炎の感染歴がある
- 肥満体型で脂肪肝を指摘されたことがある
家族のためにも、肝臓を守るという選択を
肝臓がんは、自覚症状が出るころにはすでに手遅れ──という怖さを持った病気です。
「沈黙しているから健康」ではなく、「沈黙しているからこそ注意」すべき臓器なのです。
働き盛りで、家族を支えている30代・40代の男性にとって、健康を失うことはすなわち、すべてを失うことになりかねません。
まとめ:静かな臓器には、静かに向き合う習慣を
肝臓がんは、静かに進み、静かに命を奪っていくがんです。
しかし現代では、知っていれば防げる・治せる病気でもあります。
- 検査を受ける
- 飲酒習慣を見直す
- 健診をサボらない
- 健康を「当たり前」と思わない
これらの小さな積み重ねが、あなたとあなたの家族の未来を守ります。