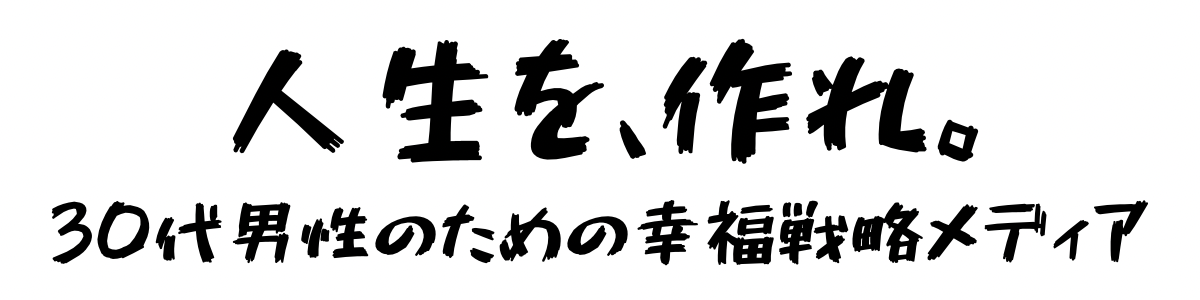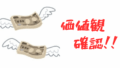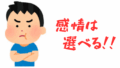資産形成に成功し、5,000万円以上の純資産を持つようになると、多くの人は「これで安心だ」と感じます。
しかし、その段階に到達しても、思ったほど生活が変わらないと感じる人は少なくありません。
むしろ、「もっと使ってもいいのに、なぜか使えない」というジレンマに陥る人も多いのです。
その理由はシンプルで、貯めることに慣れすぎて、使う力が衰えてしまっているからです。
なぜ使えなくなるのか?「資産形成マインド」の副作用
資産5,000万円を作るまでの道のりは、人によって違いますが、多くの場合は次のようなステップを踏んでいます。
- 節約の徹底
無駄な支出を削り、生活水準を意識的に下げる。 - 計画的な投資
株式、投資信託、不動産などで資産を増やす。 - 支出の抑制が習慣化
「これは必要か?」と常に考えるクセがつく。 - 資産額の増加が快感になる
使うより、増える数字を見ることに喜びを感じる。
この「節約・投資モード」は資産形成期においては最強の武器ですが、5,000万円を超えた後も続けると、お金を使うことに罪悪感を覚えるようになります。
典型的な「お金が使えない人」の行動パターン
- まだ足りないと思い込む
「インフレが進んだら…」「老後が長引いたら…」と、不安が尽きない。 - 支出に正当性を求めすぎる
「これは投資になるか?」という基準でしかお金を動かせない。 - 楽しみを先送りする
「もう少し増えたら旅行に行こう」と繰り返し、結局行かない。 - お金を増やすことが目的化する
いつの間にか「生活を楽しむため」ではなく、「数字を増やすため」に資産を管理している。
こうなると、たとえ資産が1億円を超えても、生活の満足度はほとんど変わりません。
そして年齢が上がるにつれ、使える時間や体力は減っていきます。
「使う練習」を始めるタイミングは5,000万円から
では、なぜ5,000万円が一つの目安になるのでしょうか。
- 年間生活費が500万円の人なら、資産の1%を取り崩すだけで生活費の1年分が賄える
- 平均的な日本人の生涯必要資金を大きく上回っている
- 運用益だけで生活費の半分以上をカバーできる可能性が高い
つまり、資産を減らさずに「豊かさのために使う」余力が生まれる水準です。
使う練習の具体例
- 年間予算を決める
資産の1〜2%を「豊かさ予算」として設定し、必ず使い切る。
例:5,000万円の2%=100万円。これを旅行や趣味、体験に使う。 - 時間をお金で買う
家事代行、タクシー移動、食洗機や乾燥機など、生活効率を上げるサービスや設備に投資する。 - 自己投資を拡張する
語学、資格、スポーツ、芸術など、興味のある学びに費用を惜しまない。 - 人とのつながりに使う
家族や友人との旅行、食事会、プレゼントなど、関係性を深めるために支出する。 - 寄付や社会貢献
信頼できる団体やプロジェクトにお金を投じることで、精神的な満足感を得る。
お金は使って初めて「生きた資産」になる
資産5,000万円は、日本人全体で見れば上位数%の水準です。
この時点で、すでに多くの人よりも大きな安心基盤を持っています。
その資産をただ守り続けるだけでは、「数字の奴隷」になってしまいます。
お金は、体験・時間・人間関係に変えて初めて、本当の価値を生みます。
それをせずに貯め続けるのは、使わない家具を倉庫に積み上げているのと同じです。
まとめ
- 資産形成期の「節約・投資モード」は、5,000万円を超えたら切り替えるべき
- 罪悪感なく使えるよう、毎年の「豊かさ予算」を設定する
- お金は守るだけでなく、人生を広げるために使うことで生きる
守る力と使う力の両方を持ってこそ、真に豊かな人生が実現します。
こちらもどうぞ↓