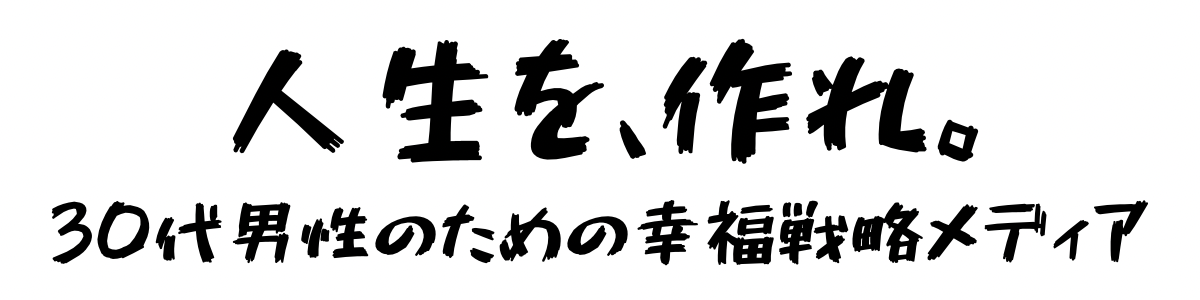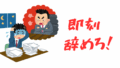組織で成果を出すには、スキルも経験も大事です。
でも、日々の仕事の中で実感するのは、
「言葉」で人は動くという事実。
管理職として働く中で気づいたのは、
本当にチームを動かすのは、会議でも指示でもなく、
“何気ない会話”の積み重ねだということです。
部下も、上司も、言葉次第で自然に動き出す。
そのために私は、普段の会話にこそ「戦略的な意図」を込めています。
雑談は“指示”の伏線になる
「最近どう? 忙しそうだね」
この一言は、ただの雑談ではありません。
私にとっては、次の依頼への布石です。
人は、自分の状況を理解してくれていると感じた相手の頼みには、自然と応じたくなるものです。
「この人、こっちの負担もちゃんと見てるな」と思わせるだけで、
依頼のハードルはぐっと下がります。
逆に、忙しさも把握せず一方的に仕事を振る上司は、信頼を失いやすい。
だから私は、何気ない雑談の中で、“相手の余力”を測る。
あとは、タイミングを見て、自然に仕事を振る。
これだけで、命令せずとも人が動いてくれます。
上司には「答え」じゃなく「納得」を渡す
部下に限らず、上司にも“言い方”は重要です。
たとえば報告を上げるとき、私はまず結論ではなく「背景」から入ることが多いです。
「結論を先に」が原則ですが、上司の性格によっては逆のほうが効果的なこともある。
なぜこういう判断をしたのか。
どんな選択肢があり、なぜこの方法を選んだのか。
この“過程”をしっかり見せることで、
たとえ結果に対して100%満足されなくても、
「まあ、そう判断するのも無理はないな」と納得してもらえる。
私の目的は「正解を出す」ことではなく、
「上司が自信を持ってゴーを出せるようにすること」です。
そのために、話し方・順序・トーンを意識して設計します。
言葉の目的は「相手を理解させる」ではない
多くの人が、「伝える=理解してもらうこと」だと思いがちですが、
私の考えは少し違います。
言葉の目的は、“行動を引き出すこと”だと考えています。
つまり、完璧に理解してもらえなくてもいい。
最終的に動いてくれれば、それで成立なんです。
たとえば部下に何かを任せたいとき、
「これは君にしかできないと思ってる」と伝えるだけで、
彼は“自分の責任”として受け止め、主体的に取り組んでくれたりします。
それが、たとえ100%本心でなかったとしても、
“相手のやる気を引き出す言葉”を選べるかどうかがポイントです。
コントロール=信頼を育てる手段
「人を言葉で動かす」というと、冷たい印象を持たれるかもしれません。
でも私の中ではそれは、“信頼を前提とした調整”です。
- 感情的にならず、
- 自分の目的を明確にし、
- 相手が納得しやすいように道筋をつける。
このプロセスを踏んで会話するだけで、
人間関係は摩擦なく進んでいきます。
これは、感情で動く人間社会において、非常に強力なスキルです。
終わりに:何気ない会話に、戦略を宿らせよう
部下も、上司も、こちらが本気で話せば、案外動いてくれるものです。
ただし、「どう話すか」に気を配る必要がある。
私は常に、「この一言が何を引き出すか?」を意識して言葉を選んでいます。
それだけで、仕事の進み方はまるで変わるからです。
なんとなくの会話で終わらせない。
日々のやり取りに、小さな戦略を込める。
それが、静かにチームを動かすコツだと思っています。
こちらもどうぞ↓