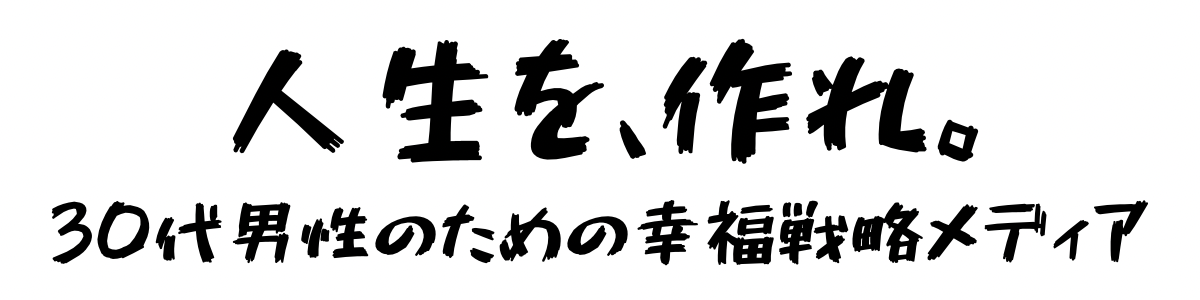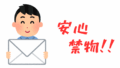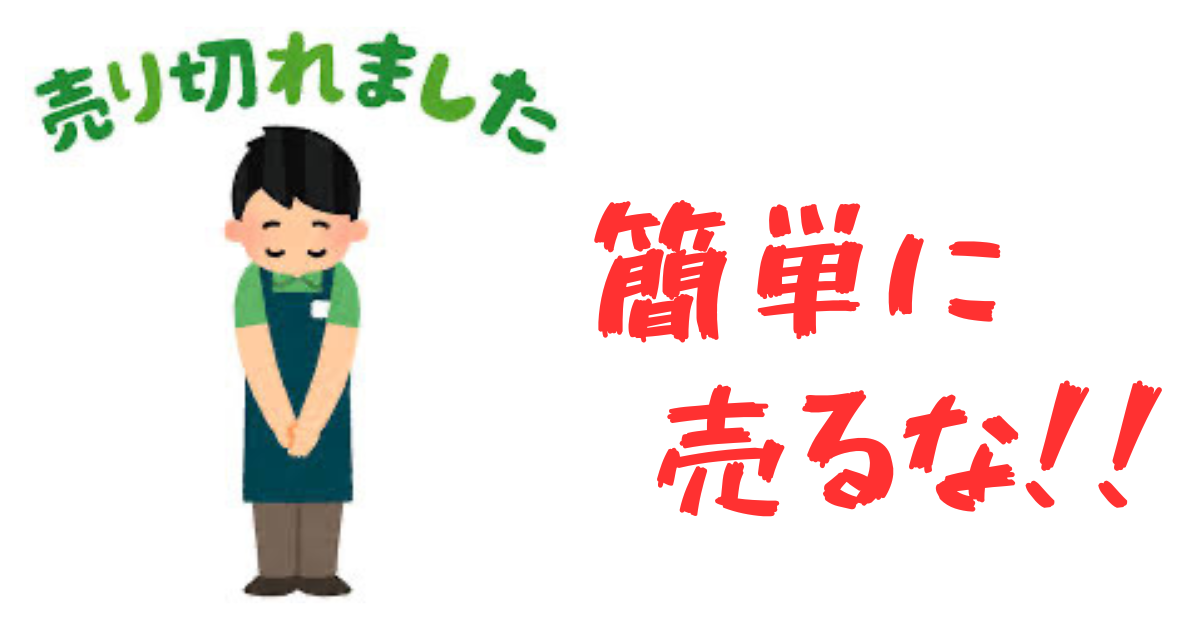
相場が急落したとき、つい「もう売ったほうがいいのでは…?」と不安になりますよね。
ETFや個別株なら、売ろうと思った瞬間にワンクリックで売れてしまいます。
そのスピード感が便利な一方で、感情に任せた“早すぎる売却”を誘発してしまうこともあります。
一方で、投資信託は売却注文を出してから実際に約定されるまでに1日〜数日のタイムラグがあります。
この「すぐに売れない」仕組みが、実は冷静さを取り戻す時間をくれているのかもしれません。
今回は、売却タイミングの「仕組みの違い」が投資家心理に与える影響について考えてみます。
ETFや個別株は、すぐ売れるからこそ“売ってしまいやすい”
ETFや株式の最大のメリットは、リアルタイムで取引できる点です。
スマホでもPCでも、タイミングを見てすぐに売却できます。
ただ、この「即売却できる環境」が、実はリスクでもあります。
相場が数%下がっただけで、「やばい、損切りしよう」と思ってしまい、
冷静な判断を下す前に、衝動的に売却してしまうことがあるのです。
本来、長期で持つべき資産でも、
「今売ればこのくらいで済む」「これ以上下がったら嫌だ」と考え出すと、
ボタンを押してしまうのは一瞬です。
投資信託は“すぐに売れない”からこそ、冷静になれる
投資信託はETFとは異なり、売却注文を出しても、実際の価格が決まるのは翌営業日の基準価額(NAV)になります。
つまり、「今日の価格で売る」ことはできません。
たとえば下落局面で、「今すぐ売りたい」と思っても、
「明日までに回復したらどうしよう?」と、自然と一度考え直す時間が生まれます。
実際に、売却注文を出すこと自体を迷い、
「やっぱりもう少し様子を見よう」とキャンセルする人も少なくありません。
これは、システム的な“強制クールダウン”とでも言えるかもしれません。
「売れなさ」が、長期投資を助けてくれる場合もある
投資信託は短期売買には不向きです。
しかし、長期的な資産形成を目的とするなら、この“即売却できない不便さ”がむしろ強みになります。
冷静さを欠いた売却は、
「安く売って高く買い直す」という最悪のパターンを生む原因になります。
その点、投資信託の売却タイムラグは、感情の暴走を抑えてくれるブレーキにもなるのです。
特に、リーマンショックやコロナショックなどのように、
短期的に急落したあとに急回復する相場では、
「売却処理の遅さ」が、結果的に資産を守る役割を果たすこともあります。
便利さはときに“リスク”にもなる
ETFや個別株のように、すぐに売れる・いつでも動けるというのは、確かにメリットです。
ただ、それは同時に「判断力を問われる」というデメリットも伴います。
市場が荒れているときにこそ、一歩立ち止まる時間が必要です。
ところが、スマホを開けば数秒で注文が通る環境にいると、
その「立ち止まる余白」が奪われてしまうのです。
便利すぎる道具は、ときに自分をコントロールしにくくしてしまいます。
だからこそ、「あえて売却しづらい仕組み」を持つ投資信託には、
長期目線での自分を守ってくれる役割があるとも言えるでしょう。
まとめ:売却タイムラグが“行動ミス”を減らすこともある
投資の世界では、「何を買うか」以上に、「どう行動するか」が重要です。
ETFや個別株は素早く対応できる反面、感情に流されやすく、
ときに“やらなくてよかった売却”を後悔することがあります。
一方、投資信託の「売れにくさ」は、
ある意味で“自分自身を守る安全装置”になり得ます。
・すぐに売れないからこそ、冷静に考える時間ができる
・その間に相場が戻って、損失を回避できることもある
・結果的に長期投資が継続しやすくなる
短期的な判断が命取りになる投資の世界において、
「行動を遅らせる仕組み」もまた、立派なリスクコントロールなのです。
こちらもどうぞ↓